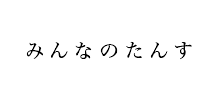野の絢(ののあや) 名前の由来
「絢」という漢字の意味は、「色糸をめぐらして取り巻いた模様。模様があって美しいさま。」と辞書にあります。
まさに私たちの工房は、野の植物からいただいた色糸をめぐらして、美しい模様の着物に織り上げる仕事をしています。自然の美を織り込み、その命のエネルギーをも着物に移すような気持ちです。その想いを現す名前として「野の絢」と付けました。
そして、論語に「素を以つて絢と為す」という言葉があります。美人が装うことでさらに美しくなるという解釈もあるようですが、私は、人それぞれの本質・素質を活かした装いをすることで、さらに美しくなるということなのではないかと思っています。
野の絢シリーズ(紬・上布・木綿)は、お召しになる方がいっそう美しく輝くような着物でありたいと願い、創作していきます。
また、京都丹後地方で藤織り(原始布)を伝承してきた女性たちは、織った藤布のことを「のの」と呼んできました。「のの」とは、神仏・日月など、尊ぶべきものをさしていう幼児語でもあります。偶然の音の一致かもしれませんが、布(ぬの)も神仏・日月と並ぶ、尊ぶべきものではないでしょうか。
「のの=布(ぬの)」を織るその原点を忘れぬよう、音の響きも大切にしたいです。
野の絢シリーズ(紬・上布・木綿)の特徴
① 国産の天然繊維
紬(絹):真綿の手紡ぎ糸
上布(麻):苧麻、大麻の手績み糸
木綿(木綿):和綿の手紡ぎ糸

② 草木染
植物から抽出した液で染めます。
自然と調和する美しく深みのある色合いがえられ、染める植物によっては薬効も得られます。
例:
藍(あい):抗菌・排毒・免疫系の強化
蓬(よもぎ):血液循環や自律神経の調整。殺菌・抗黴作用など

③ 地機(じばた)による手織り
風合いや手触りがよく、着心地も良いです。
※地機(じばた)とは
5世紀ころから日本で使用されたとみられる原始的な手織機で、「いざり機」とも呼ばれます。現代では、本場結城紬、小千谷縮、越後上布という最高級品でのみ使用されています。経糸(たていと)を腰で吊って、テンション(張り具合)を身体で調節しながら織るため、糸に負担をかけず、機械では織れない繊細な手紡ぎ糸を織る事ができます。織り手の身体的な負担が大きいけれど、地機で織った布は、風合い、着心地の良さで群を抜いています。